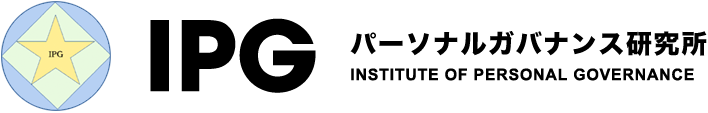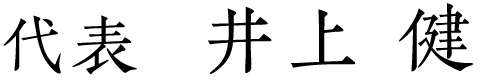私の略歴
私は1957年に東京で生まれました。その後もずっと東京で育ち、高校は都立青山高校、大学は早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業しました。私の人生の大きな転換点となったのが、学生時代の世界一周の一人旅でした。わたしは、大学2年生を終えた段階で1年間休学をし、400日間をかけて世界を回りました。1979年の2月にバックパックを背負って早稲田大学の大隈講堂を出発し、カナダのバンクーバーを振り出しにして、北米、南米、アフリカ、ヨーロッパ、アジアとまわり合計35カ国を訪ねて、1980年の3月にフィリピンのマニラから東京に戻ってきました。当時の私は21~22歳でしたが、インターネットはもちろん旅行ガイドブックもほとんどありませんでした。ちなみに「地球の歩き方①ヨーロッパ」が創刊されたのが1979年9月です。ですから、経験することすべてが目新しく、まさに生まれて初めての経験ばかりでした。この400日間の一人旅の経験はあまりに多く、ここに書き尽くすことはできないのですが、地球をぐるっと回って感じたことを一言でいうと、「この地球はなんと多様なのだ、多様な自然と生物、多様な人間社会と文化、この多様性は本当に美しく、素晴らしい」というものでした。日本のようなほぼ単一民族、単一言語の同質的な社会で生まれ、育ってきた私には特にこの地球世界の多様性が新鮮で素晴らしいものだと感じたのです。そして私は、この時に、よし、自分の一度きりの人生はこうした多様な地球社会をつなぐ国際協力の仕事に使おうと心に決めました。
早稲田大学を卒業してから、私はイギリスにあるサセックス大学の開発研究所(IDS)の修士課程に留学しました。そこで2年間、開発学を勉強してから、国連を中心とする国際機関に国際公務員として就職しました。当時も今も国際機関は日本のような終身雇用制ではありませんから、雇用の保証は全くなく、一つの契約が終わるたびに数か月の浪人生活をして何とか次のポストを見つけるというありさまでした。私が渡り歩いた国際機関の場所と名前だけを書きならべると次の通りです。まずワシントンDCにある世界銀行、ついでトリニダード・トバゴの国連開発計画(UNDP)、タイのバンコックにあった国連カンボジア人道支援事務所、カンボジアに展開した国連PKO(UNTAC)、ソマリアに展開した国連PKO(UNOSOM II)、スイスのジュネーブにあった国連ボランティア計画(UNV)とその移転先のドイツのボン、コソボに展開した国連PKO(UNMIK)、東京に本部のあるアジア生産性機構(APO)、そして東ティモールに展開した国連PKO(UNMIT)です。その後は父の介護のために東京に戻りましたが、父の没後はモロッコのラバトでアラビア語とイスラム文化を1年ほど勉強した後、また東京に戻り、政府機関である国際協力機構(JICA)に2020年まで勤めました。日本に戻ってきてからは、獨協大学、東洋大学、京都女子大学、桜美林大学、創価大学、ハノイ大学日越大学院などで非常勤講師を務めてきましたし、そのほか東京大学、早稲田大学、上智大学、明治大学、法政大学、二松学舎大学、筑波大学、立命館大学、同志社大学など多くの大学で短期間の講義を行ってきました。また、国連訓練調査研究所(UNITAR)、日本国際平和構築協会、国連システム元国際公務員日本協会、市民によるガバナンス推進会議、アムネスティ日本、日本国際連合学会、国際開発学会、国連システム学術会議などのメンバーでもあります。2019年には、今上天皇の即位の大礼に参加するために来日されたコソボのサチ大統領から、私のコソボでの活動に対して「人道と平和への貢献を表彰する大統領メダル”聖マザーテレサ“」を授与されました。
私の専門分野
私が国際協力に志してからすでに40年余りが過ぎましたが、私が専門的に携わってきた分野は、①持続的開発、②人道支援、③平和維持構築活動、④生産性向上、そして⑤民主的ガバナンスです。持続的開発に関しては、UNDPやUNVで活動してきましたし、現在は国連の2030アジェンダ(SDGs)について大学で教えています。人道支援はカンボジアやソマリアの難民や避難民への支援活動をしてきました。平和維持構築活動は、カンボジア、ソマリア、コソボ、東ティモールでの4つの国連PKOに参加しました。生産性向上に関しては、APOで工業部長を務めていました。そして民主的ガバナンスについては、東ティモールで国連の首席ガバナンスオフィサーを務め、その後はJICAで民主的ガバナンスのシニアアドバイザーを務めました。
これから私のやりたいこと
既に書いたように私は、私の人生を国際協力の分野で生きて行くと決めています。その拠点がこれまでは、国連であったり、JICAであったりしました。そしてこれからは、パーソナルガバナンス研究所です。私がこの研究所を立ち上げた理由はいくつかあります。
第1は、日本にいる難民とその家族を支援したいと考えているからです。私は、多くの紛争国で仕事をしてきました。そこで、普通の市民が戦禍に追われ、難民や国内避難民として苦しんでいる現状を目の当たりにし、彼らを支援してきました。祖国に戻れない難民は、難民キャンプを出て他の国への再定住を目指します。そうして難民のごくわずかが日本にやってきて難民として受け入れられたり、認定のための申請をしたりしているわけです。ところが、はるばる戦禍を逃れて日本にやってきた人々が日本社会では必ずしも温かく迎え入れられていない現状があることに気づきました。まだ日本人の多くは、日本は日本民族だけの国だと考え、外国人はお客様としておもてなしするか、労働者として短期間働いてもらったラすぐにおかえりいただくものだと考えている人が多いようです。私はこうした考えは、現在のグローバル社会の中では通用しないと思います。もちろん、無規制に誰から問わず日本に入れて無期限に滞在を認めるというようなことはすべきではありません。これからは、難民の方々を良き市民として日本社会に受け入れていくことが、少子高齢化が進み人口が減少していく日本社会にとっても意義のあることです。
第2は、そのためにファイナンシャル・プランニング(FP)の手法と資格を活用したいと考えているからです。FPは金儲けの技術だと誤解している方がまだ多いかもしれませんが、FPの本質は、お金の視点から人生を見直し、お金に困ったりお金に溺れたりすることなく、個々人が自分の人生の価値観に基づいて夢や目標を実現していくことです。私は、日本に在留している難民や外国人労働者などの移民の方々が良き市民として日本に定住するためには、彼らが普通の市民として生活していくための経済的基盤をしっかりと持つことが不可欠だと考えています。日本に来た最初のうちは政府や篤志家からの支援も必要かもしれませんが、なるべく早く日本語を覚え、仕事に就き、地域社会に溶け込んでいかなければなりません。その基盤となるのが安定した家計です。私は、こうした人々を支援するためのスキルを身につけたいと考え、ファイナンシャル・プランナーの資格を取りました。ファイナンシャル・プランナーの業務については、ファイナンシャル・プランニング事業のページに詳しく説明してあります。このスキルを中核としながらも、これまでの40年以上にわたる国際協力活動で築いてきた知見や人脈を活用していきたいと考えています。
第3は、自分の活動の社会的立ち位置をはっきりしたいと考えているからです。私は、これまで海外では国際連合、国内では国際協力機構(JICA)という大きな組織で仕事をしてきました。どちらも名前を知らない人はほとんどいないくらい著名な組織で、そこの職員であるというだけで社会的地位と信用を得ることができました。ところが、こうした組織を退職し一人になってみると自分個人の社会的立場が、いかにあいまいで不安定なものであるかを実感しました。元xxの職員というだけでは、ほとんどの方は「xxは知っているけれどあなたの名前は聞いたことないなあ」で終わってしまいます。ですから、私自身のこれからの社会的立場を明確にするために、パーソナルガバナンス研究所という組織を立ち上げ、明確なミッション、ビジョン、事業目的をもって国際協力の仕事を続けていこうと考えたのです。もちろんパーソナルガバナンス研究所と私自身が社会的に認知され、一定の信用を得るまでには相当の実績と歳月が必要であることはわかっています。しかしその第一歩として、まず、このホームページで皆様に自己紹介とご挨拶をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、この研究所を拠点に私がこれからやりたいことは、次の4つの事業です。
1. パーソナルガバナンスに関する研究事業
2. 日本に在留している難民と難民申請者への支援事業
3. ファイナンシャル・プランニング事業
4. 国際問題に関する講義・講演事業
それぞれの事業の具体的な内容は事業の説明に関するページをご覧ください。
また、IPGに関するコメントやご質問のある方は、いつでもお問い合わせください。